土地に関する3つの測量とは?
不動産売買の場面で必ずと言っていいほど登場する「測量図」。
しかし、実は測量図にはいくつか種類があり、どの図面かによって土地の信頼性や価値、売買条件が大きく変わることをご存じでしょうか。
今回は、不動産取引で代表的な3つの測量として
①確定測量図 ②現況測量図 ③地積測量図
それぞれの意味と価値基準について、不動産業者の視点と測量士の視点の両面から解説します。
①確定測量図(かくていそくりょうず)
●意味・特徴
確定測量図とは、土地の境界を法的に確定させた図面です。
専門の土地家屋調査士が、隣地所有者や道路管理者など関係者全員と立会いを行い、境界ポイントに「境界標(杭)」を設置して作成します。
言い換えれば、隣地との境界線や面積を公式に認め合った証拠です。
●不動産業者の視点
売買においては最も価値の高い測量図とされ、
確定測量が完了している土地は、買主からの信頼度が高く、
価格交渉でも有利に働くことが多いです。
特に建物解体後の土地や相続・空き家の売却では、確定測量の有無で成約率が大きく変わります。
●測量士の視点
確定測量は時間とコストがかかります。
隣地立会いの調整に数ヶ月かかることもあり、
トラブルがあるとさらに長期化する可能性も。
しかし、それを乗り越えた分だけ、将来まで安心できる境界情報が残ることが最大の価値です。
②現況測量図(げんきょうそくりょうず)
●意味・特徴
現況測量図は、現時点で見えている境界(ブロック塀、フェンス、擁壁など)を基準に測った図面です。
隣地との合意確認までは行わず、あくまで現地の状況を表すものになります。
●不動産業者の視点
「建物付きのまま売却する」「投資用として利回り重視の取引」などでは現況測量で十分な場合もあります。
しかし、境界の真実性は保証されないため、将来的にトラブルが起きるリスクは残るという前提理解が必要です。
●測量士の視点
現況測量は早い、安い、最低限の確認が可能というメリットがあり、
売却前の情報整理や査定の資料として便利です。
ただし、現況の構造物が正しい位置にあるとは限らないため、
「参考図面」としての扱いになります。
③地積測量図(ちせきそくりょうず)
●意味・特徴
法務局に備え付けられた登記簿面積の元となる測量図で、土地分筆や合筆時に作成された公的な図面です。
ただし、古いものは測量技術が現代と違い、誤差が大きい場合があることも重要ポイントです。
●不動産業者の視点
土地情報の確認材料としては重要ですが、
地積測量図だけでは売買に十分と言えません。
面積差が出ることが多く、坪単価の高い地域では差額の金額も大きくなるため、
最終的には現況測量や確定測量が求められるケースがほとんどです。
●測量士の視点
昭和期の測量は誤差が大きいことが多く、
実測すると数坪違う例は珍しくありません。
地積測量図は「過去の参考資料」であって、
現代の法的な境界を確定するものではないと理解する必要があります。
まとめ:測量の違いを理解することが損を防ぐ
| 測量の種類 | 信頼性 | 売買価値 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| 確定測量図 | ★★★★★ | ◎ 最も高く評価 | 境界紛争の回避・土地価値の最大化 |
| 現況測量図 | ★★★☆☆ | ○ 普通 | 早期売却・参考情報 |
| 地積測量図 | ★★☆☆☆ | △ 参考資料 | 登記情報の確認 |
土地売却では、測量の種類によって価格や買主の安心感が大きく変わります。
逆に、測量の違いを知らずに進めることが、後悔やトラブルの原因になりかねません。
不動産業者としては、売主様の状況や目的に応じて最適な測量を提案することが重要であり、
測量士としては、将来トラブルにならない境界の確立が使命です。
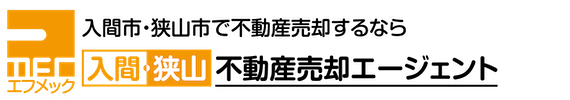







どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎04-2965-0622